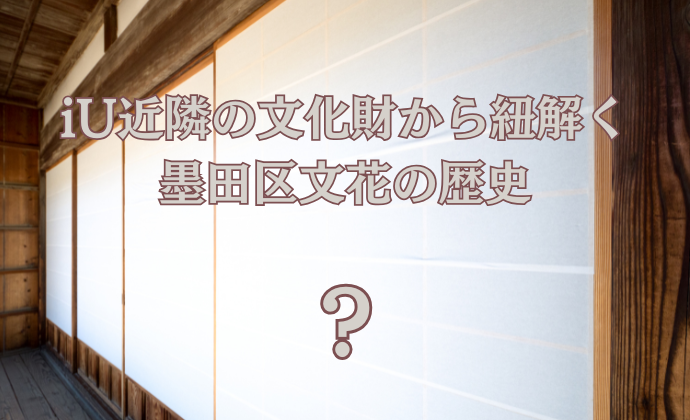ところ変われば「食」も変わる。「カツカレー」にみる食の柔軟性

「カツカレー」プリーズ、の意味
2025年になった、と思ったらもう2カ月が経とうとしています。iUから卒業式の案内が届き(実際には行けないので、オンラインで視聴します)、「もうそんな時期!?」と驚いています。
まだまだ寒いロンドン。我が家がある通りは小さめの桜が植わっている「桜並木通り」なのですが、芽吹きの様子はまったくありません(↓写真)。春が来るのはまだまだ遠い、そんな日々を送っています。

ある寒~い夜、近所に住む友人P君(イギリス人)からチャットが入りました。
「今日寒いね~。久し振りに、ハナコの“Katsu Curry”食べたいよぉ。辛めでお願いします」
はいはい、承りました。近々P君&友人数名と一緒に我が家でカレー会をする約束をしたのですが、この時彼が私にリクエストした「Katsu Curry」は「カツが添えられたカレー」のことではないのです。日本のカレールーで作る、ごく普通の「日本風カレー」が食べたい、と言っているのです。
ではなぜわざわざ「カツカレー」と言うのか?が今回の本題です。
イギリスで日本風カレーは既に定着済み
日本風のカレーは、日本食レストランでは何十年も前から提供されている定番メニューです。私はイギリスに来てから数えきれないぐらい日本風カレーを作り、イギリス人&欧州人に食べてもらっていますが、皆大好きです。欧州人の口にとても合うようです。
かつては「知る人ぞ知る」存在だった日本風カレーですが7~8年前にロンドンで大ブレイクし、その後イギリス津々浦々に広がりました。
「火付け役」として知られる店はたくさんあるのですが、よく語られるのは下記2つの飲食店です。1店目はイギリス全土にチェーン展開しているカジュアル系日本食レストラン「Wagamama」。1992年に創業し、カレーは創業当時から提供していましたが、チキンカツを添えた「チキンカツカレー(↓@wagamama_uk – instagramのキャプチャ画像)」 をいち早く紹介したお店と言われています。2000年代初期から中期にかけて定番メニューとして確立されました。

もう1店はロンドンを中心に展開している日本食テイクアウト店「Wasabi」(2003年創業)。寿司や日本風弁当を販売するチェーン店で、「チキンカツカレー(↓)」は創業当初から定番メニューとして提供しています。手軽なランチとしてロンドンのビジネス街で人気となりました。

ブレイクの理由は「チキンカツ」をセットにしたこと
日本風カレーがなぜ突然ブレイクに至ったのか? それは、「カレー」だけではなく「チキンカツ」と合体させてメニュー化したところがポイントです。
カレー&ご飯だけではなく「カツ」も加えることで見栄えと満足度をプラスさせ、魅力的なメニューにしているのですが、ここで使われているのは「トンカツ」ではなく、「チキンカツ」です。日本人的には「カツカレー」に使われるのはトンカツのイメージが強いと思いますが、イギリスで広く販売するためには“絶対に”「チキンカツ」である必要があったのです。それはなぜか?
それはイギリスが多文化共生の国だからです。イスラム教やユダヤ教等、豚肉を食さない宗教の信仰者が多く暮らす国ですが、鶏肉は多くの宗教において「OKな食品」です。幅広い層に食べてもらえるよう、「チキンカツ」をつけてカレーを販売したところ、人気となりました。
これにより、日本風カレーは「チキンカツカレー」または「カツカレー」という名称で広まりました。日本のカレー文化も「カツ」と言う言葉の意味を知らない人たちにとっては、「日本のカレーはチキンカツがセットで食べるもの」「カツカレー=1つの単語」として認識されていきました。
こんな経緯があるので、人々はカツが入っていないカレーのことも「カツカレー」と言いがちです。友人P君も私に「カツカレー、プリーズ」と言ったのも、そういう背景があってのことです。
やっと認知されてきた「カツ」
ブレイクから5年程は「カツの入ってない『カツカレー』」をいろんな場面で見てきたのですが(笑)、ここ1~2年でやっと「カツ」が「肉(または野菜)を揚げたもの」だという認識も広まり始めました。大手スーパーが「KATSU」として、調理済みのチキンカツを販売したことで「あ、カツってカレーとセットの言葉じゃないのね」と人々が気づき始めたのです。こちらのカツ(↓)は、高級系スーパーがお惣菜コーナーで販売しているものですが、大人気で見ているそばからバンバン売れていました。家でオーブンに温めてカリッとさせてから食べるのですが、なかなかの味でした。

こんな風にイギリスで「独自の道」をたどっている日本のカレーですが、基本的に「日本で食べられている日本のカレー」を知らない人たちに向けて開発されているものなので、今でもよく不思議なもの見掛けます。例えばこちら(↓)はカレー風味のケチャップですが、ここにも「KATSU」の文字が入っています。もちろんケチャップの中にカツが入っているわけではなく「カツカレーと言う名の日本風のカレーの風味のケチャップ」と言う意味です。

他にもカレー風味のさらっさらのスープ(カツは入っていない)が「カツカレースープ」として提供されていたり、「カツマヨネーズ(カレー風味のマヨネーズ)」「カツカレー餃子」「カツカレー焼きそば」「カツカレーバーガー(チキンカツにカレー風味のソースがかかったハンバーガー)」とか、カレー風味だと何でも頭に「カツ」または「カツカレー」がついている商品もあり、なかなか愉快です。
食も言葉も「その地」で発展していくもの
日本からイギリスに観光できた人や、イギリスに暮らし始めたばかりの日本人にとっては「こんなの日本のカレーじゃない!」と言いそうなものもた~くさん見かけます。また言葉もそう。「カツカレーじゃなくて『ただのカレー』です」と言い直したくなる場面もたくさんあります。でも食も言葉もそういうものなのでは?とも思います。「元ネタ」が何であれ、どこか別の国・地域で導入されたなら、その土地で愛された形で発展していくものなんだと思います。
日本に帰国すると、イギリスで見かけるサイズの1/10ぐらいの大きさのフィッシュ&チップスや、中にあんこが入ったスコーンを見かけます。イギリス人が見たら「なに、これ?」と思うかもしれません。でも食べやすいし、美味しいし、それが日本の風土に合う食べ方なんですよね。
ちなみに上記に紹介した「Wagamama」も「Wasabi」も日本人の経営ではありません。非日本人の眼差しで日本風カレーを美味しいと思い、イギリスに暮らす人たちにとっての「美味しい」「食べたい」を研究した結果、ブレイクにつながりました。「カツカレーと言えばトンカツでしょう」「カレーとカツは別のもの」としていたら、イギリスが「カツカレー大好き国」にはならなかったと思います。「オーセンティック(正統派)」にこだわるのも1つの方法ですが、その土地にあったものにアレンジする柔軟さが成功につながった例だと思います。
News Flash!
— Wasabi (@Wasabi_UK) April 1, 2021
More products.
More Sainsbury's.
More Katsu happiness.
We are now in more than 1000 Sainsbury’s! Pop into your local or order online to enjoy our freshly prepared Wasabi home bento meals, gyozas, K-wings and more! 🍣@sainsburys#homebento #wasabiuk #sainsburys pic.twitter.com/7exIK9vPpr
ブレイクの種を柔軟な心で探してほしい
起業家を育てる大学として知られるiU。身近なところに転がっている「ブレイクの種」を柔軟な心で育ててほしいなと思い、過去にこのカツカレーの話を「バーチャル研究室」で話したことが数回あります。学生さんがとても興味を持って聞いてくれたことを、今回の「カツカレー、プリーズ」の会話をしながら思い出しました。
さて、我が家のカレー会。いつもはカツなしの「カツカレー(=ただの日本風カレー)」なのですが、今回は「カツカレー」にしてみましょうかね。来てくれる人に「豚肉NG」の人はいないので、「ポークカツカレー」にしてようかしらん。友人たちの反応が楽しみです。